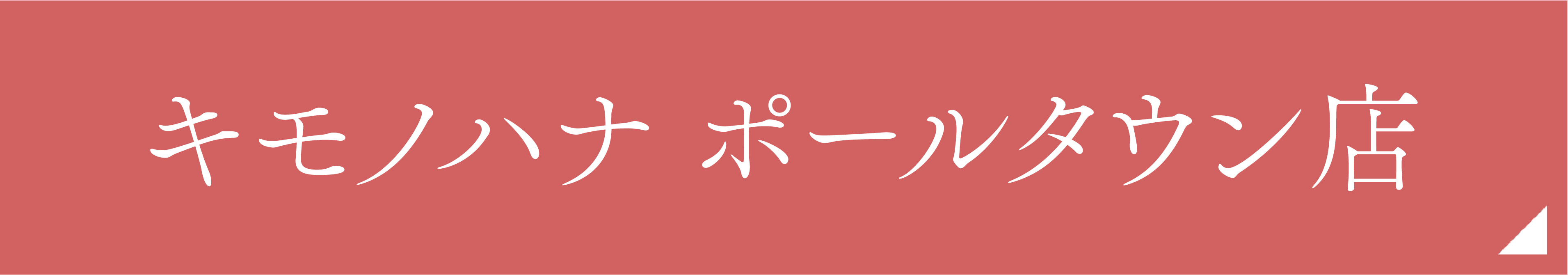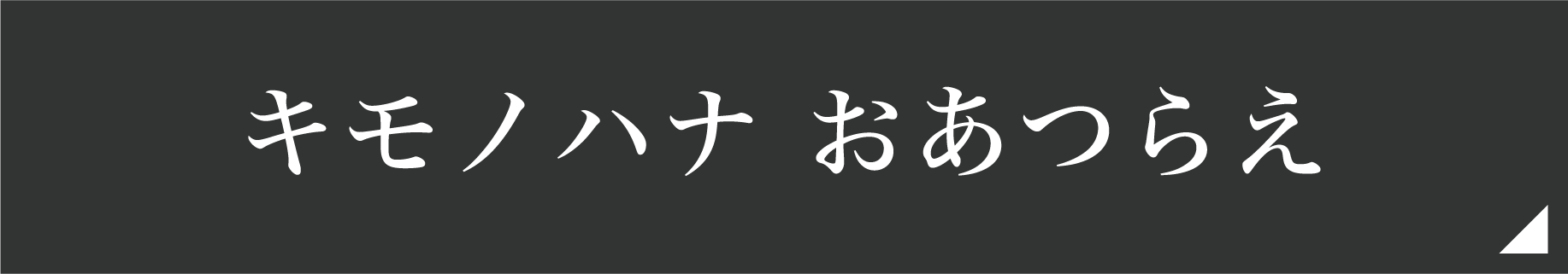銘仙?錦紗?アンティークによくある生地をご紹介!
- 投稿日:2021.09.20
- カテゴリ: アンティーク、リサイクル着物
こんにちは!コモノハナの高山です。
まだ日中は少し暑い時もありますが、
朝や夜は肌寒くなってきましたね。
近付いてくる秋の気配。
コモノハナでも、このイベントを開催いたします!
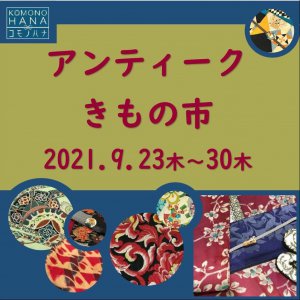
アンティークきもの市
9月23日(木)~30日(木)
前回の好評を受け、第2弾を開催いたします!!
以前もアンティーク着物についてのブログを書かせていただきました。
前回の記事の内容は、アンティーク着物とは何か?などのご紹介から入りましたね。
そこで今回は、少し踏み込んだ内容として…
押さえておきたい、アンティークならではの生地
をご紹介したいと思います!
銘仙(めいせん)

アンティークがお好きな方なら聞いた事があるのではないでしょうか?
それくらい、アンティーク着物=銘仙というイメージが浸透していると思います。

銘仙は分類としては織りの着物。
ジャンルとしては普段着にあたります。
張りのある生地
絣と呼ばれる、柄の境目がぼやけた織り方
が大きな特徴です。

銘仙は元々、織子(機織りを仕事にする人)さん達がくず糸を使って自分用に作っていたそうです。
大正時代から昭和初期にかけて、その軽さやお手頃な値段で人気が出てきました。
丁度その時代、西洋から入って来たアールデコやアールヌーヴォーなどの大胆な柄、
鮮やかな発色の化学染料などを使用し、華やかな銘仙が数多く出回りました。
当時の女学生達も袴の上に愛用していたみたいです。
詳しくは、こちらのブログでご紹介しています!
いつの時代も、女子学生はカワイイを追い求める物なのですね~
お召

お召の正式名称はお召し縮緬。
縮緬と名前が付いていますが、織りの着物です。
織りは基本的に普段着なのですが、お召しは織りの中では一番格の高い生地なので
セミフォーマルなどにも着ていただける物もあります。
江戸時代は、お殿様への献上品として作られていたみたいです。
お殿様がお召しになる着物というのが名前の由来だそうですよ。

キュっと目が詰まった、艶のある触り心地が特徴です。
お召は現代でもお茶席などの着物として人気があります。
現代ものは無地感の強いシックな物が多い印象です。

アンティークのお召しは、大胆な柄が織り込まれている物も多いですよ。
錦紗(きんしゃ)

正式名称は錦紗縮緬。
染めの着物です。
こちらはとにかくやわらかい!
しぼが細かく、トロリとした質感です。

通常の縮緬よりも発色が良いそうで、
アンティーク着物では晴れ着などの
フォーマルによく使われています。
とても薄くて繊細な生地なので、優しく扱う事が大切です。

また、加工もしやすいので、リメイクの材料などにも人気があります。
ダメージの大きい物などは、新しく作り替えてしまっても素敵かもしれませんね!
以上、アンティークならではの生地をまとめてみました。
もちろん、普通の紬、縮緬、綿などのアンティークもあります。
現代でも、お召しや銘仙は作られているんですよ。
ですが、現代物とアンティークってやはりそれぞれの良さがあって、
趣が違うと思うんですよね。
当時流行した生地などを眺めながら
何故流行したのか、
どんな人達が着ていたのか、
これを着てどんな所に行っていたのか
そんな事を考えるのも、楽しいです。
100年近く前の着物達が持っている物語ごと、アンティーク着物を愛して下さると幸いです。
***ニッポンのおしゃれは無限大***
和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)
〒060-0063
札幌市中央区南3条西4丁目1番1
さっぽろ地下街ポールタウン内
TEL/FAX:011-221-3661
mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp
**コモノハナオンラインショップ**
**コモノハナLINE**
**コモノハナのSNS**


 Instagram
Instagram
 Facebook
Facebook
 Twitter
Twitter