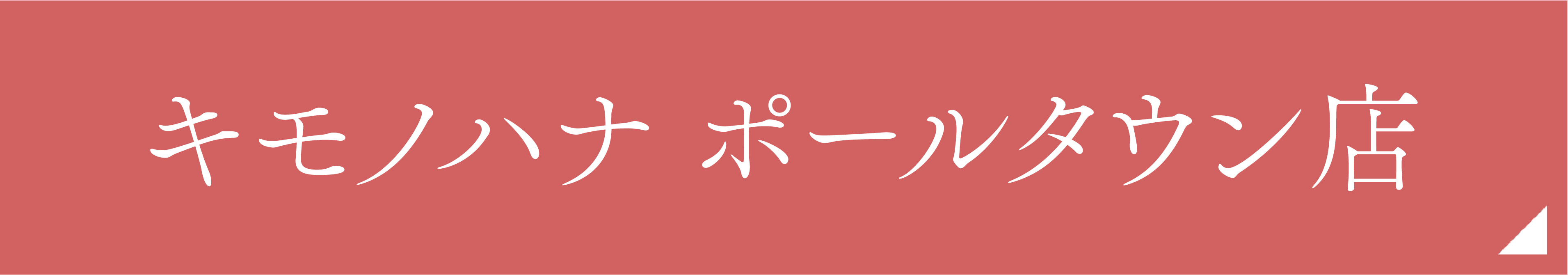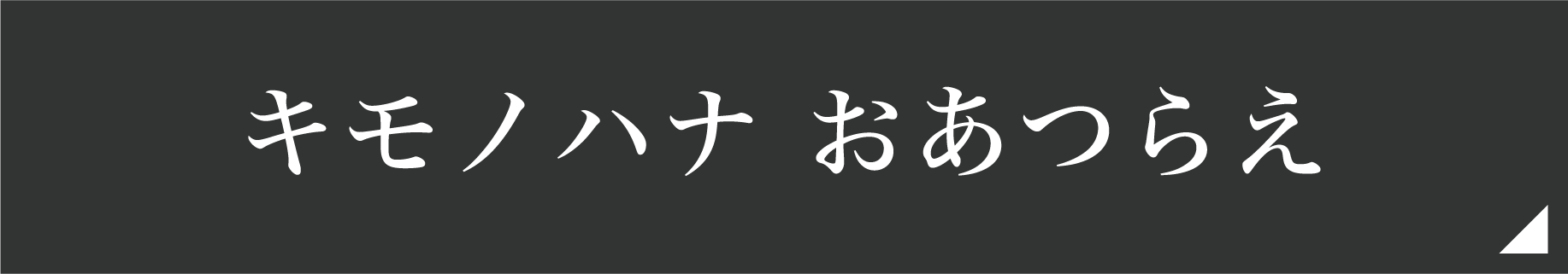高山の着物雑学帖 その2 ~四君子を語る~
- 投稿日:2021.01.15
- カテゴリ: 着物雑学帖
こんにちは!コモノハナの高山です。
先月は着物雑学帖の第一回目を投稿させていただきました。
ちょっと緊張でしたが、見ていただいた方からは
暖かい反応がいただけたのでとても嬉しいです。
ありがとうございます!
さてさてそれでは

着物雑学帖 その2
をお送りいたします!
…のっけから少女漫画調でとばしてみました(笑)
花を背負っているので、ちょっと華やかにしてみようと思っただけなんです…
目に星が入っている私の自画像はさておき、背後のお花にご注目下さい。
こちらの4つは、実はとある組合せなのです。
(私の絵だとわかりづらいかもしれませんが…何とか目を凝らして見て下さい)
大丈夫でしょうか?
ではそろそろ答え合わせをいたしますね。
描かれている植物は
蘭、竹、菊、梅
この4つの組合せは
四君子
と呼ばれています。
四君子。
着物がお好きな方は聞いた事のある方も多いのではないでしょうか。
礼装の着物などによく使われる、吉祥文様でもあります。
そもそも何故四君子と言うのか?
いつ頃からある物なのか?
植物はそれぞれ何の意味があるのか?
今回はその疑問に迫って行きたいと思います!
四君子とは何か?
まずは単語に入っている「君子」という言葉に注目してみましょう。
君子とは中国で「徳と賢と儀を備えた人物」の事だそうです。
現代だと「優しくて頭が良くて礼儀正しい人」って感じでしょうか。
全て足りない私からすると、そんな人になってみたいものです…。
そして蘭、竹、菊、梅はそれぞれが君子の特性を持っているという事で
北宋(900年頃~1100年代)頃に四君子と呼ばれるようになったようです。

中国で栄えた四君子は、室町頃に日本に伝わったと言われています。
最初は水墨画の題材として用いられたそうです。
・春(蘭)夏(竹)秋(菊)冬(梅)と四季を網羅している
・これらを描くにあたって基本的な筆運びを全て学べる
と入門編として欠かせない題材だったとか。
その後、江戸時代頃に文人を中心として絵だけでなく様々な文様に使われていったようですね。
当時は絵師さんが副業で着物の図案を描いていたそうですから必然的な流れだったのかもしれません。
それぞれの意味とは?
さて、そんな四君子の4つ。
それぞれどんな意味があるのかをご紹介していこうと思います。
蘭
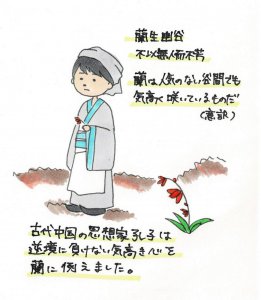
蘭は香りよく、気高い王者の花と言われています。
また、人里離れた山にひっそりと咲いている姿は
高貴でありながら決して驕らない謙虚な姿をイメージさせてくれます。
蘭は冬の花と言われていますが、春に咲く春蘭という区分けもありまして。
四君子では春を象徴する物とされていますので恐らく後者だと思われます。


ちなみに蘭はたくさんの種類がありまして、着物に描かれるのは左の和蘭が多いです。
胡蝶蘭やカトレアなどは洋蘭。明治以降に日本に入ってきました。
洋蘭は季節を問わず用いられると言われています。
こうして見ると別の花みたいですよね!
竹

竹は真っ直ぐに伸び、年中青々とした葉を繁らせています。
そこから成長、生命力などの象徴と言われています。
素直で純粋、溌剌とした若者のイメージになるのでしょうか。
竹から生まれたかぐや姫の物語のように、竹は昔から不思議な力があると言われていました。
また、古くから家具、楽器、日用品など生活に根付いている馴染み深い物でもあります。
ちなみに、竹は北海道にないというのはご存じですか?
こちらにも「タケノコ」は採れるんですが、あれはヒメタケやネマガリタケといって
笹の仲間だそうですよ。初めて聞いた時は驚きました。

これは数年前京都に旅行に行った時の竹林です(確か高台寺だったかな?)
「ああ~確かにこれはこっちでは見ないなあ」と再確認したものです。
菊

菊は寒さ忍び寄る秋の中、美しく咲き誇る姿を見せてくれます。
別名「陰君子」とも呼ばれているそうですよ。
世俗に交わらずひっそりと山野に住む賢人の事だそうです。
冬へ向かい、他の草花が枯れていく中に鮮やかな花を咲かせる様子と重なる気がしますね。
菊は不老長寿の象徴とも言われ、菊の節句とも言われる「重陽の節句」では
花びらを浮かべた酒を飲み、健康を願ったそうです。
こちらのブログで語らせていただきましたので、気になる方はぜひ♪
菊繋がりではありますが…私は時代物、現代ものを問わず怪談を読むのが大好きなんです。
江戸時代の怪談集「雨月物語」に出てくる「菊花の契り」というお話がとても印象に残っています。
とある若者達の深い友情の物語です(個人の感想です)怖いだけでなく泣ける要素もありますので
気になる方はぜひ調べてみて下さいね。

ちなみに札幌では毎年11月に「さっぽろ菊まつり」が開催されています。
今年は地下歩行空間で見事な花が咲き乱れていました!
眼福眼福(*^^*)
梅

梅は「花の魁」と呼ばれ、花の中で一番早く春を知らせてくれると言われています。
厳しい寒さを耐え忍び、美しい花を咲かせる姿は忍耐や強靭さを象徴しているそうです。
コツコツと努力を重ねる人、といったイメージでしょうか。そっと見守りたいですね。
梅で有名なのは学問の神様と言われる菅原道真公。
政争に敗れ九州に左遷される際、自宅の梅の木に歌を詠んで別れを惜しむと
その木が飛んでやってきたという「飛梅伝説」は有名なエピソードです。
ちなみに道真公が祀られている太宰府天満宮、北野天満宮はどちらも梅の紋を掲げています。
梅は本来、2月~3月頃が見ごろですが、北海道では当然ながら咲いていません(笑)
こちらの梅の季節は4月後半~5月前半。
この時期は梅も桜も一斉に見る事ができるんですよー!


上の写真は札幌の平岡公園「梅まつり」の時の写真です。
梅ソフトクリームも売っていて、甘酸っぱくてとてもおいしかった~!
昨年は中止だったので、2019年の時の写真です。
今年は開催されると良いのですが…。
以上が四君子のご紹介になります!
何気なく見ていた着物や帯の柄。
でも調べていくとそこには深い深い歴史があるのですね。
四君子の草花達から感じ取れる君子像、とても魅力的ですね。
美しい容姿に個性的なキャラクター。
私はそれで

アイドルグループを連想してしまいました(笑)
なにせ伝統と歴史がありますからね。国民的アイドルですよ!
蘭、竹、菊、梅
あなたは誰推しですか?
私は箱推しです!
さて、二回目の着物雑学帖、いかがでしたか?
私も段々楽しくなってきてしまいまして…
次はアレにしようかな?コレを語ろうかな?と色々考えてしまいます。
皆様からのリクエストもお待ちしておりますので、
これを知りたい、これを語って!などがありましたら
高山に教えて下さいね。
それから、前回もお話いたしましたが
着物は長い歴史の中で様々な人々、土地で育まれてきた物です。
地域や年代によって、名称やルールの違いが存在します。
ご自分の知っている事と違ったとしても「習った事と違う、間違っている」
と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れましょう。
着物の知識に「絶対」はありません。
所説あり
という事で楽しんでいただけると幸いです。
高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。
来月また、お会いいたしましょう!!
***ニッポンのおしゃれは無限大***
和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)
〒060-0063
札幌市中央区南3条西4丁目1番1
さっぽろ地下街ポールタウン内
TEL/FAX:011-221-3661
mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp
**コモノハナオンラインショップ**
**コモノハナLINE**
**コモノハナのSNS**


 Instagram
Instagram
 Facebook
Facebook
 Twitter
Twitter